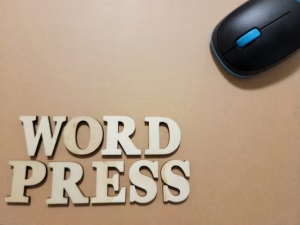【入稿前に最終チェック!】Illustratorで印刷物デザインするときの7つの重要注意点
「Illustratorで素敵な名刺やフライヤーができた!さあ、印刷会社に入稿だ!」
でも、ちょっと待ってください!そのデータ、印刷に適した設定になっていますか? Illustratorを使って自由にデザインできるのはとても楽しいですよね。けれど、印刷物を作る際には、Webデザインとは異なるいくつかの「お約束」があります。これらを見落とすと「思ったような色で刷り上がらなかった」「端が切れてしまった」なんて悲しい結果になることも。
今回は、そんな失敗を防ぐために、Illustratorで印刷データを作成する際に特に注意したい7つのポイントを分かりやすく解説します。入稿前の最終チェックリストとしてもご活用ください!
1. ドキュメント設定の基本:カラーモードは「CMYK」、ラスタライズ効果の解像度は「高解像度」
まず、Illustratorで新規ドキュメントを作成する段階が肝心です。
- カラーモードは「CMYK」に!
- パソコンやスマホの画面は「RGB(光の三原色)」で色が表現されますが、印刷インクは「CMYK(色の三原色+黒)」で表現されます。最初からCMYKで作成しないと、印刷時に色が大きく変わってしまう原因になります。
- 設定方法:
ファイル>新規でドキュメントを作成する際、「詳細オプション」などでカラーモードを「CMYKカラー」に設定します。ドキュメント作成後ならファイル>ドキュメントのカラーモード>CMYKカラーで変更できます。
- ラスタライズ効果の解像度は「高解像度(300 ppi以上)」に!
- ドロップシャドウやぼかしなどの「効果」は、Illustrator内部でピクセル画像(ラスター画像)として処理されます。この解像度が低いと、印刷したときに効果部分が粗くギザギザに見えてしまいます。
- 設定方法:
効果>ドキュメントのラスタライズ効果設定を開き、「解像度」を「高解像度(300 ppi)」またはそれ以上に設定します。(印刷会社から指定がある場合はそれに従いましょう。一般的には300~350ppiが推奨されます。)
2. サイズと向き:仕上がりサイズを正確に、アートボードの向きも確認
当たり前のようですが、意外と見落としがちなのがドキュメント(アートボード)のサイズと向きです。
- 仕上がりサイズを正確に設定しましょう。
- 名刺なら一般的に「91mm × 55mm」、A4フライヤーなら「210mm × 297mm」など、作りたい印刷物の実際の仕上がりサイズでアートボードを作成します。
- アートボードの向き(縦長・横長)も確認しましょう。
- 意図したレイアウトになっているか、縦と横を間違えていないか、しっかり確認してください。
3. 塗り足し(ブリード):必須設定!端までキレイに印刷するコツ
デザインの背景色や写真などが、仕上がりサイズの端まである場合、「塗り足し」が絶対に必要です。
- なぜ必要?
- 印刷後、紙は仕上がりサイズに断裁されますが、機械のわずかなズレで、デザインの端に白いフチ(紙の色)が出てしまうことがあります。これを防ぐために、仕上がりサイズよりも外側(通常上下左右各3mm程度)までデザインをわざとはみ出させておくのが「塗り足し」です。
- 設定方法:
- 新規ドキュメント作成時に「裁ち落とし(または塗り足し、ブリード)」の項目で設定します(例:上下左右すべてに「3mm」)。
- 作成後なら
ファイル>ドキュメント設定から設定できます。 - 重要: 塗り足し領域までしっかりと背景色や画像を配置してください。
4. トンボ(トリムマーク):断裁位置の目印を忘れずに
「トンボ」は、印刷会社がどこで紙を断裁するかの目印となるマークです。
- 役割: 正確な仕上がりサイズに断裁するために必要です。
- 作成方法:
- 仕上がりサイズの四角形オブジェクトを選択した状態で、
オブジェクト>トリムマークを作成(古いバージョンでは効果>トリムマーク)。 - 日本式トンボと西洋式トンボがありますが、印刷会社の指示がなければ日本式で問題ないことが多いです。
- 注意: トンボは通常、塗り足し領域の外側に作成されます。
- 仕上がりサイズの四角形オブジェクトを選択した状態で、
5. 文字のアウトライン化:フォントのトラブルを確実に防ぐ!
デザインで使用したフォントが、印刷会社のパソコンに入っていない場合、別のフォントに置き換わってしまったり、文字化けしたりするトラブルが起こります。これを防ぐのが「文字のアウトライン化」です。
- アウトライン化とは?
- 文字情報を図形(パス)情報に変換することです。図形になるため、フォント環境に依存しなくなります。
- 手順:
- すべてのロックを解除し、隠されたレイヤーがないか確認します。
選択>すべてを選択します。書式>アウトラインを作成を実行します。
- 超重要: アウトライン化すると、文字としての再編集は一切できなくなります。 必ず、アウトライン化する前の編集可能なIllustratorデータ(.aiファイル)を別名で保存しておきましょう。
6. 画像の配置:リンクか埋め込みか?解像度も要チェック!
Illustratorに配置する写真やビットマップ画像は、「リンク」と「埋め込み」の2つの方法があります。
- リンク配置
- Illustratorファイルとは別に画像ファイルが存在し、それを参照している状態。ファイルサイズを軽く保てます。
- 注意点: 入稿時にはIllustratorファイルと一緒に、リンクしている全ての画像ファイルも送る必要があります。 リンク切れを起こすと画像が表示されません。
- 埋め込み配置
- 画像データをIllustratorファイル内に直接取り込む方法。ファイルサイズは大きくなりますが、Illustratorファイルだけ送ればOKです。
- 一般的に推奨されることが多いのは「埋め込み」です。 リンク切れの心配がありません。
- 確認・変更方法:
ウィンドウ>リンクでリンクパネルを開き、画像を選択してパネルメニューから「画像を埋め込み」を選択できます。
- 画像の解像度も確認!
- 印刷に使用する画像の解像度は、一般的に実寸で300~350dpi(ppi)程度が推奨されます。これより低いと、印刷時に粗くぼやけて見える原因になります。Web用の72dpiの画像などは印刷には不向きです。
7. オーバープリント設定:意図しない色の重なりに注意(上級者向け)
「オーバープリント」は、ある色のオブジェクトが下の色に重ねて印刷される設定です。意図して使う場合は有効ですが、意図せず設定されていると、思った色と異なる仕上がりになることがあります。
- 特に注意したいのは「黒」のオーバープリント:
- スミ(K100%)の文字や細い線が下地の有彩色に影響されないように、スミにオーバープリントを設定することがあります(リッチブラックとの使い分け)。
- しかし、広い面積のスミベタにオーバープリントが設定されていると、下地のデザインが透けて見えてしまうことがあります。
- 確認方法:
- オブジェクトを選択し、
ウィンドウ>属性で属性パネルを開き、「オーバープリント」のチェックを確認します。 表示>オーバープリントプレビューで画面上の見た目を確認できます。
- オブジェクトを選択し、
- 初心者の方へ: よく分からない場合は、むやみに触らないのが無難です。印刷会社によっては自動で処理してくれる場合もあります。不安な場合は事前に印刷会社に相談しましょう。
【おまけ】特色や透明効果は、事前に印刷会社に確認を
- 特色(スポットカラー): CMYKの掛け合わせでは表現できない特別なインク(金色、銀色、蛍光色など)を使う場合。
- 透明効果: オブジェクトに適用する「乗算」「スクリーン」などの描画モードや不透明度の設定。
これらはデータ作成方法や印刷の可否が印刷会社によって異なる場合があります。使用したい場合は、デザイン制作を始める前に印刷会社に確認するのが最も確実です。
まとめ:入稿前の最終チェックで、理想の印刷物を!
Illustratorでの印刷物デザインは、細かな設定が多く感じるかもしれませんが、一つ一つ確認することで、イメージ通りの美しい仕上がりにつながります。この記事が、あなたの作品作りのお役に立てれば幸いです。
創人塾では、Illustratorの基本操作はもちろん、こうした印刷データ作成の実践的なノウハウまで、プロのデザイナーが丁寧に指導しています。もっと深く学びたい、自信を持ってデータ入稿できるようになりたいという方は、ぜひ創人塾の講座もチェックしてみてくださいね!あなたのデザインが、素敵な印刷物として形になるのを楽しみにしています!
創人塾はあなたのデザインキャリアをしっかりサポートします。
筆者プロフィール
丸谷 香織 Kaori Maruya
Web・グラフィックデザイナー/ディレクター/創人塾Webデザインコーチ・リーダー
神奈川県横浜市出身。総合広告代理店で新規開拓営業を学び、その後ディスプレイデザイン会社で新規開拓営業・企画・デザイン・製作・現場施工を経験。2005年6月、フリーランスデザイナーとしてディスプレイデザイン・製作・施工を主軸に営業開始。初年度売上げ8桁達成で2006年10月法人成り、株式会社 Coconeil 設立。企業・店舗や団体・省庁などのイベントのWebデザイン・実装、ロゴデザイン、紙媒体のデザインと印刷を主軸に活動中。さらに近年では、駆け出しだった当時の自分を助けてくれた人たちへの恩返しの意味合いもあり、デザイン添削やアドバイスをする傍ら、複数のオンラインデザインスクールでデザインコーチ、講師としても活動。2025年3月、各分野のエキスパートたちとオンラインデザインスクール創人塾を開校、Webデザインコーチ・リーダーに就任。